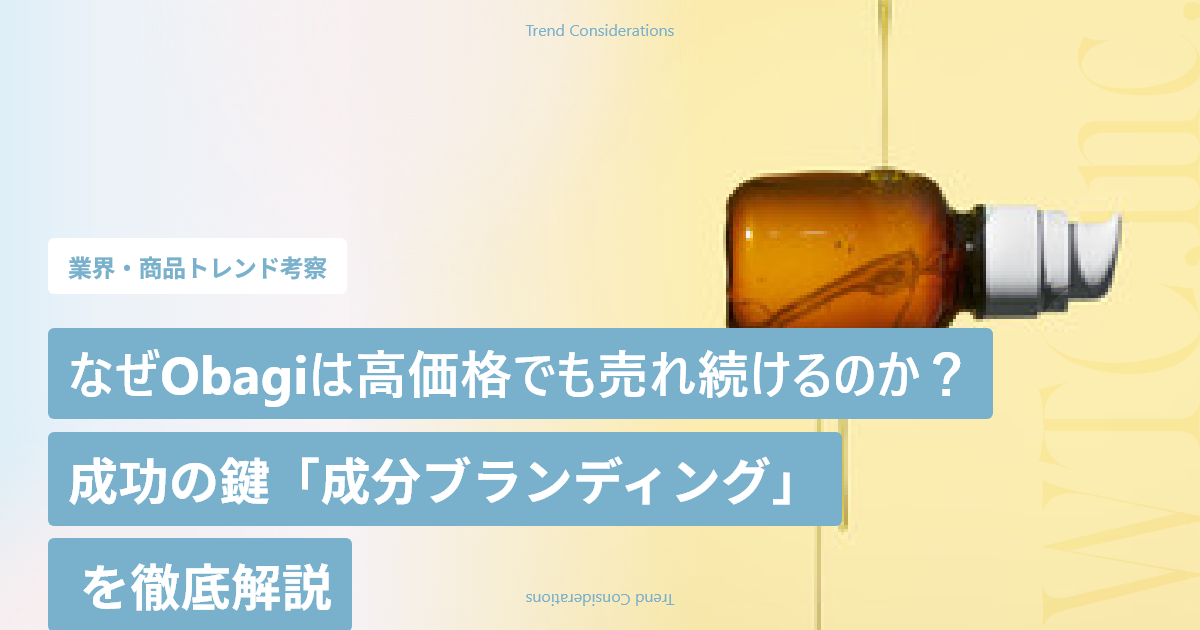ロート製薬が展開するスキンケアブランド「Obagi(オバジ)」は、皮膚科学に基づいた高機能スキンケアとして知られています。高価格帯にも関わらず安定した売上を維持しており、その独自の販売戦略やブランド構築法に多くの企業やマーケターが注目しています。
本記事では、Obagiがどのようにして競合ブランドとの差別化を図り、高価格帯市場で支持を獲得しているのか、その販売戦略を中心に解説します。

引用:obagi公式サイト
目次
Obagi Cセラムとは
『Obagi Cセラムシリーズ』は、ロート製薬が展開する高濃度ビタミンC配合の美容液です。「肌に科学を。」というブランドメッセージのもと、研究開発力と科学的エビデンスを背景に信頼を構築してきました。多くのスキンケアブランドが「シミ」「ハリ」といった結果を訴求する中、Obagiは“ビタミンCそのもの”を前面に押し出し、「この成分があるから結果が出る」というロジカルな説得軸を確立しました。結果として、消費者の中で“Obagi=ビタミンC”という明確なイメージが形成されています。
Obagiはなぜ高価格でも売れるのか?
「美白」「エイジングケア」といった言葉がスキンケア市場を席巻する中、ロート製薬の「Obagi C セラムシリーズ」は一般的な効果訴求とは一線を画しています。このブランドの主役はたった一つの成分であるビタミンCです。高価格帯でありながら、多くのユーザーに長く支持され続けている理由は、「成分ブランディング」と「SNS時代の消費インサイト」を的確に捉えた戦略にあります。また、Obagiは創業以来「ビタミンC×肌科学」という明確なテーマを一貫して掲げています。スキンケア市場では多くのブランドが流行に合わせて商品ラインを拡大しますが、Obagiはあえて専門商品の深掘りによってブランドの軸を強化しています。これにより、他社にはない研究に裏付けられた安心感を確立しています。Obagiが同価格帯の競合ブランドよりも選ばれる理由は、価格で競うのではなく、科学的信頼性と体感できる効果で差別化してる点にあると言えます。
成功要因①:「ビタミンC=Obagi」という成分ブランディングの確立
Obagiの最大の強みは、成分とブランドが一体化している点です。高濃度・安定性・浸透力といった専門性の高いキーワードを積極的に発信することで、単なる化粧品ではなく「科学的な美容液」というポジションを確立しました。多くの他社製品がビタミンC誘導体を使用するなか、オバジCセラムシリーズは純粋なピュアビタミンC(アスコルビン酸)にこだわって配合しています。さらに、濃度別にラインナップを用意することで、肌質や悩みに合わせて選べるようにしています。このように、成分を“効果”ではなく“信頼の象徴”として訴求することで、高価格でも納得感のあるブランド価値を創出しています。

引用:obagi公式サイト
成功要因②:SNS時代の“成分買い”トレンドとの親和性
情報過多の時代だからこそ、広告のイメージだけでなく、自分の肌で結果を出せる『確かな成分』を求める消費者が増えています。だからこそ、近年、X(旧Twitter)やInstagramでは、「この成分が入っているから買った」という“成分買い”トレンドが拡大しています。ユーザーは製品の効果だけでなく、配合成分や濃度といった情報から購入判断を行うようになりました。Obagiはこの流れと非常に親和性が高いブランドです。「高濃度ビタミンC」「ピュアVC」といった専門性のあるワードがSNS上で自然に語られ、ブランド発信ではなく生活者主導のUGC(口コミ)によって信頼が拡散しています。専門性と共感のバランスが、SNSでの持続的な話題化につながっています。
成功要因③:ユーザーを巻き込む多面的なプロモーション設計
Obagiは、ユーザーを巻き込む形でブランド体験を設計しています。
• 美容家・専門家など、信頼性の高いインフルエンサーを起用したレビュー発信
実際に、田中みなみさん、森香澄さん、福田彩乃さんなど著名人がobagiを愛用していることを公表しています。
• 「#オバジCセラムチャレンジ」などのSNSキャンペーン
この試みは、3日間や1週間の短期集中ケアから、1ヶ月程度の継続使用を通じて、肌の変化を感じることを目的としています。多くのユーザーがInstagramやX(旧Twitter)、美容系口コミサイトなどで「#オバジCセラムチャレンジ」などのハッシュタグを使い、使用前後の肌状態や使用感を投稿しています。オバジCセラムの主成分であるピュアビタミンC(アスコルビン酸)が、毛穴、くすみ、乾燥小じわ、ハリなどの肌悩みにどのようにアプローチするかを体感します。
• ポップアップイベントや店頭体験を通じたリアルコミュニケーション
これらの施策はいずれも、“成分の信頼を体験で確かめる”というメッセージで統一されています。発信者・体験者・ブランドが一体となり、「語りたくなるブランド」を作り上げている点が特徴です。
まとめ
Obagiの成功は、「ビタミンCが人気だから」ではありません。科学的エビデンスとSNS時代の共感構造を結びつけ、成分そのものをブランド価値へと昇華させたことが最大の要因です。今後のスキンケア市場では、「どんな成分が入っているか」だけでなく、「その成分をどのように信頼させるか」がブランドの成長を左右します。Obagiは、“成分ブランディング”という新たな価値創造モデルを提示した先駆的な事例といえるでしょう。